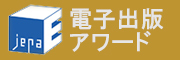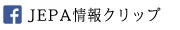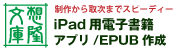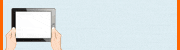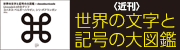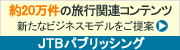直江屋 紙田 彰
先頃、久しぶりに一般書籍の売り場を訪れて、一般書籍、文芸、資料関係の出版物の 点数が激減しているのに驚いてしまった。
その書店は、近所の比較的大きな書店なのだが、いつのまにか、雑誌、読み捨てレベ ルの書籍、パソコン関係の本ばかりになっていて、わたしが今までふつうの本と考えて いたものが書棚に見当たらないのである。
思えば、もう20年ほど前から、「読み捨て」出版物が、大量消費の時代を象徴するよ うに出版と書店との間に横溢し、それまでたしかに存在していた、出版と書店という特 別な関係をもつ流通の現場が、出版文化という理念から大きく離れはじめたような気が する。
やせがまんする出版社や、口をへの字に結ぶ書店が持ち堪えられなくなったのであろ うか。
出版は、書店は、根本的なものを見失ってしまったのではないか。そのような思いが、 先の驚きの中身である。
どういうことかというと、出版というものが「ビジネス」という尺度で測られすぎて いはしまいかということだ。そして、その結果、出版流通の縮小と出版文化の萎縮、空 洞化を招来させているのではないか。
出版には、文化を蓄積する側面と、文化を創造するという側面がある。また、文化を 継承させるという面がある。
文化という、人間の知的体験を未来へ向けて橋渡しするということは、人間的営為の 中で特段にすぐれた能力である。そこには、未来の人間を信じ、人間の可能性を信じ、 また、そのような営為を可能とする人間の高潔を信じる勇気がある。
出版とはただのビジネスではない、というところから、捉えなおす必要があるのでは ないだろうか。
現状のような大不況下では、ビジネスという局面だけで考えれば、近視眼的な諸策を とらざるをえないし、それが根本的な解決にならないということも自明だ。ビジネスだ けで出版を論ずることが新しいなどというのは、この不況でもはや通用するべくもない。
しかし、出版そのものが、出口の見えない苦境にあるばかりではなく、新しい時代へ の産みの苦しみを経験していることも事実である。良くも悪しくも、その新時代への可 能性は、デジタル技術革新をどう取り込んでいくかにしかない。
デジタル出版の試みは、単に時代に追随するというようなところから、出版の可能性 をそこに見出していくというところに到達している。 電子出版、あるいはデジタル出版が、出版というものを根本から変えていくのは間違 いないし、だからこそわれわれはこの分野で歩を進めているのだ。 しかし、根本から変えるというのは、単にこれまでの出版の延長線上にデジタル出版 があるということではないはずだ。 出版は、文化を人間の歴史的展開の中に伝えるという大きな使命がある。
出版のデジ タルデータベース化は、まさに、文化の遺伝子情報としてアーカイブし、それをいつで も利用することで人類の可能性を広げるという意味がある。 このデジタルデータベース化は、単に現状のデジタルデータビジネスやネットワーク ビジネスに躍らされているから必要だというのではなく、出版が文化としてあるための、 いわば存立の根拠であり、義務であるはずだ。
ところで、出版は「本をつくり、これを広める」ことがその役割なのだろうか。 たしかに、広めるという目的が「本」にあるというのは間違いのないところだ。だが、 広めるのは「本」そのものではなく、「本の魂」とでもいうべき、思想であり、文化で ある。
また、「本を読む」という行為は祈りに端を発するとしても、「読む行為」を通じた 文化創造が営まれたからこそ、現代がある。
これまでの出版は、印刷技術をバックボーンにしていたから、「本」は物質的に固定 したもの、静的なものであり、作り手側からの一方向的な情報付与という性格を持つも のであった。そのため、造本、編集などの「本の形態」についての技術・加工技術をも 含めて「本の全体」を構成し、「本の魂」の外側にある「本」の存在を強固にしていっ た。
出版文化において、この「本づくり」、「本の広め方」という技術も、またたしかに 大きな側面なのである。
しかし、それでもあえて言おう。「本」が「本の魂」そのものであっても、文化創造 をするのは「本の魂」と交感した人々なのである、と。
わたしは、近頃、次のような言葉に疑念を持ちはじめている。
ひとつは、「出版社は、本づくりのプロだ」というもの。デジタル出版になろうが、 ネットワークで展開されようが、読者がカネを払ってでも読むに価するものを提供でき るのは出版社だけだというものだ。
また、「出版の仕事は本をつくることだ」「本は読むためのメディアだ」という出版 の常識――。
わたしは、出版文化とは、本を作る技術ではなく、文化としての理念、思想にこそそ の本来があるはずだと考えている。
逆説的な問いかけであるが、「本づくりでなければ本当にだめなのか?」という疑念 を呈してみよう。
出版のデジタル化によって、「本」という静的なものから、動的な「データ」という 形で、コンテンツ自体が大きく変化している。
そして、このデジタルコンテンツははたして「読書をするため」のものなのだろうか。 「本」は読まれることを前提にしてつくられるが、このコンテンツは「読まれるためだ け」に読者の目前にあるのだろうか。
読者とコンテンツとの関係は、まず、蓄積された大量のデータに容易にアクセスでき るということ、また、自分のパソコンに取り込み、これを創造的素材、創造的原因とす ることができるということで、いわば「本の魂」との直接の交感が可能なのである。
このように考えていくと、「本は読まれるためにある」ということから逸脱する段階 に来ているのかもしれない。
読者もまた、「本を読むための存在」ではなくなったのである。読者は、情報に対し て受け身に立つものではなく、より能動的かつ活性化された存在に変貌していくのであ る。
つまり、読者に一方的に情報を与えるという考え方から抜けきれなければ、「本づく り」を基本にした既存の出版を脱し、新たなコンテンツ文化を展開することはできない だろう。
作り手と受け手という固定した考え方ではなく、相互に作用しあい、相互に新しい文 化を創造していくという、これまでとは異なった関係が取り結ばれるのである。
デジタル化とネットワーク化は確実に出版ビッグバンをもたらすが、これは改めて出 版文化を問い直し、新しい文化創造というコンセプトを打ち立てるだろう。
そのためには、真に出版の財産とは何か、真に出版は生き残れるのか、あるいは創造 的な場所を本当に産み出せるのか、が問われるだろう。
デジタル出版は、おそらく、「本を作る」ということから脱却することで、文化とし ての出版のありようを根本から変えていくのではないだろうか。