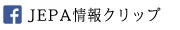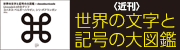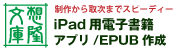1 黎明の章
岩波書店と電子出版の縁は深い。CD-ROM版の電子広辞苑がソニー・富士通・大日本印刷との共同開発によって富士通製ワープロ用に発売されたのが1986年だった。昨年(2017年)刊行された社史『岩波書店百年』には、「本格的辞書の電子出版のトップランナーとしての地位を固めた」(871頁)と記されている。その年にJEPAは旗揚げされた。社内では部局から独立した形で「ニューメディア研究室」というのが立ち上げられていた。
当時まだ入社していなかった私は、そこでいかなる業務が進められていたのか、知るよしもない。その後、「印刷冊子体出版物以外のメディアによる文化伝播の可能性を追求する」(同845頁)とされたニューメディア開発室(のちに改称)は、ビデオ・CD・DVDブックスの数々の独自コンテンツを編集し出版していった。
2 停滞の章
2000年代に入るころから、携帯電話とインターネットの普及にともなって、出版業界は次第に電子書籍の製作・配信に事業を特化していくようになっていった。2010年の電子書籍元年を迎えたものの、掛け声のわりにその年の電子書籍の売り上げは前年割れだった。しかし、大震災の直後に経産省が実施した「緊デジ」事業で、その成否は置くとして、電子化率は一挙に上がった。
岩波書店は緊デジに乗ることを潔しとせず、版面再現性が心もとないEPUBに不安を覚えながら、電子書籍ビューアの目まぐるしい開発・販売競争に翻弄されながら、また電子書籍ストアでの売れ行きがはかばかしくない実情にもどかしさを覚えながら、既刊書からの電子化を遅々とした歩みで進めていった。なにせ4万点近い創業以来の書籍のバックリストがある。掘り起こしの選書作業と電子化処理のさなかにも、新刊は続々と刊行されていく。緊デジに浮力を得て離陸した出版他社が軽やかに新刊同時の電子化を進めていくのを横目で見ながら、電子出版において先頭を切っていたはずの岩波は、水をあけられていく。私はそんな思いで、一人ほぞをかんでいた。
3 転機の章
社内組織上も、個人的な嗜好においても電子書籍に縁のなかった私が、電子出版にかかわることになったのは、電子出版以外の業務がきっかけであった。当時私は編集局で新刊の企画編集業務のかたわら、復刊書目選定の取りまとめを担当していた。復刊活動のなかで、PODは当初、通常重版が難しい学術書の蘇生手段としてしか位置づけられていなかった。ところが、高額少部数の販売モデルは、岩波のような学術全ジャンルの豊富なタイトルを抱える出版社にとって、選書さえ間違えなければ確実な販路として位置づけられることが実感できた。とりわけ1970年代から2000年ころまでの活版組版末期に、業界としては好況期において出版された、長らく品切れていた書目は、PODでの注文が絶えない。やはり文化というものは手間と資金を惜しみなく投入すればするほど、時間の風雪に耐える知的資産へと彫琢されていくものなのだ。電子書籍も同様なのではないか? 電子書籍ストアで歓迎されている安価で手軽なコミックを中心としたコンテンツだけに目を奪われず、電子で読みたいという読者の要望に応えていこう。
眠ったままの広大な資産の鉱脈を掘り起こしていきたい。そのために選書と製作のための一貫した指揮系統を備えた組織体を立ち上げようとして、2014年4月に電子出版部の製作機能に編集部の選書機能を合体させて結成されたのが、デジタルコンテンツ(DC)事業部であった。創業から101年目のことであった。高額学術書の電子化は、一般読者向けの電子書籍ストアにはなじみにくい。そこで丸善雄松堂や紀伊國屋書店が開発運用する学術機関向け電子書籍配信インフラに、PODでの選書と同様の選書ラインで、学術書・レファランス書を中心にコンテンツを提供した。研究者・大学図書館には歓迎され、アメリア・中国はじめ海外の日本研究を手がける大学図書館にも販路を広げていった。
4 苦悩の章
やがてDC事業部は壁にぶつかった。組織上、製作系統と編集系統を合併させただけでは、出版社コンテンツをめぐる関連業界の技術開発とビジネスモデルの多様化の速さにはとても対応できないのである。いま出版社をコンテンツ・プロバイダーとする知識産業において生起していることは、コンピュータの電子工学と編集の眼識だけでは解決のつかない、150年来継続してきた、日本の近代出版システムに構造的変化を迫るものなのだ。従来の版元―取次―書店ルート圏外で、通信・配信業者を中心とするプラットフォーマーたちが提供するサービスに読者が大きく吸い寄せられている。
読者側の読書習慣の変化も大きい。紙本へのこだわりは特にスマホ世代の若年層にいけばいくほどなくなっている。典型的なのは児童書市場だ。これまで未成年読者はクレジット決済ができないため、電子書籍化は遅れていた。そこに、ベネッセコーポレーションが運営する「進研ゼミ」受講者向けの「まなびライブラリー」の普及によって、小中高校生向けの急速な拡大と定着が実証された。ただ私はこれを単純に紙から電子への移行の過渡期だとは見ていない。読書のツールが紙・電子、さらにはオーディオと多様化しているのであり、同じコンテンツでも検索は電子で、解釈は紙で、閲読(閲聴?)はオーディオで、といった風に、同一ユーザーがワンソース・マルチメディアで使い分ける習慣が育ちつつある。またコンテンツのインターフェースにおいても、リアル書店やネット書店での購入、あるいは図書館での借り出しと多様化している。電子書籍ストアにおいては、1点ごと買い切りだけでなく、読み放題のサブスクリプションモデルが定着している。公共図書館においては、貸し出しは無料だが、版元との間ではサブスクリプションや定額有期制などの新たな販売モデルが浸透しつつある。
この構造的変化に直面して、コンテンツホルダーとしてはプラットフォーマーたちとどう協業していけばいいのか? 電子においては再販価格が維持されず、版元に価格決定権はない。いったいどんなユーザーがどんなコンテンツにどんな風にアクセスしているのか? プラットフォーマーは、販売実績はもちろんのこと、顧客情報や市場動向をビッグデータの情報処理技術によって瞬時に正確に詳細に把握している。その情報精度は従来の出版社や書店の比ではない。従来の営業系の経験知でも、この構造的変化には対処できない事態に直面しているのである。
5 再編の章
頭を抱えた私はJEPAの主催する若手出版人が集う茶話会に足を運んだ。同業他社の会員の方々に向かって、電子出版推進のためにいまの出版社にはどのような組織体を備えることがふさわしいものなのか、率直に悩みをぶつけた。そのとき、にこやかに「ライツを中核に置くといいですよ」と一言ご助言をくださったのが茶話会モデレーターのJEPA岡山将也さんであった。「ライツ?」「はて知財のことか? それならウチは編集総務課が著作権管理を担務しているぞ。……いや待てよ、海外出版社への翻訳権はそことは別か……」ほかにも社が抱えるライツを洗い出してみた。オーディオ化権、舞台などの副次化権、他社文庫や試験問題などへの転載許諾……。直面していた困難はもっぱらデジタル化の技術的障壁だけだと思いこんでいた。じつは既成観念の壁が立ちはだかっていたのだ。ライツは版権保護のための手続き業務としてしか受けとめてこなかった。みずからの意識改革から始めなければ。
同業他社の数社のライツビジネス担当部署にも聞き取りをした。判明したことは、デジタル化をめぐっては、どの社も同じような問題で悩み苦闘していること、対処方法は各社各様であること、各社の組織には各社の歴史といきがかりが反映されていること、共通の正解はないこと、業界や環境の変化に応じて変化していくことに躊躇しないこと。かくして今年2018年の10月、社内関係各部署の各部員を再編して、ライツマネジメント部を立ち上げた。
6 飛躍(に向けて)の章
変化しているのは出版業界だけではない。学術界も教育界も大きな変化のさなかにある。クリエイティブコモンズが世界的潮流になっているいま、法的根拠となる著作権法の理念と運用も変わりつつある。変化はめまぐるしい。1年後にはまた違う風景が視界に広がっているかもしれない。かといって静観を決めこめばビジネスチャンスを逸する。老舗企業にありがちな前例踏襲という計策は最適解への道を閉ざす。この変化へのアクションプランを策定する際に、5つの方向性を定めるよう肝に銘じている。デジタル化、新規事業への参入、異業種他社との協業、同業他社との有志連合、グローバルなライツビジネスの展開。とくに拡大する中国市場を見逃してはいけない。彼らの巨大な脳髄の胃袋は、コンテンツに渇している。とりわけ日本のコンテンツを貪欲に摂取している。そのことは、目下の対外版権ビジネスの実績が実証している。
これまで変化ばかりを強調してきた。だが、日本の近代出版150年の歴史を経ても変えてはならないことがある。それは出版物を創造し続け、また既刊書を内容・データ両面で更新していくコンテンツメーカーとしてのたゆまぬ営為である。私は出版人としての矜持を失わないために、絶えず自問していたい。お前は自社出版物を知っているか? 既刊書を在庫圧力としてしか見てはいないか? 出版物を知財としてとらえているか? 知財をシェアする信頼関係を著者と築いているか? お前に市場の声は届いているか?